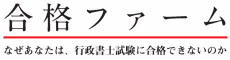基礎法学 (H17-1)
裁判に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 裁判所は、法令適用の前提となる事実の存否が確定できない場合であっても、裁判を拒否することはできない。
イ 最高裁判所は、憲法その他法令の解釈適用に関して、意見が前に最高裁判所のした裁判または大審院のした裁判と異なるときには、大法廷で裁判を行わなければならない。
ウ ある事件について刑事裁判と民事裁判が行われる場合には、それぞれの裁判において当該事件に関して異なる事実認定がなされることがある。
エ 裁判は法を基準として行われるが、調停などの裁判以外の紛争解決方法においては、法の基準によらずに紛争の解決を行うことができる。
オ 上告審の裁判は、法律上の問題を審理する法律審であることから、上告審の裁判において事実認定が問題となることはない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
解答 2
今回は基礎法学の問題ですが、過去問は繰り返し出題されることのいい問題例です。
例えば、肢イは、平成19年度問題1の肢5で、肢エは、平成15年度問題2の肢3および平成18年度問題1で、肢オは、平成15年度問題2の肢5で、それぞれ類似問題が出題されています。
このように何度でも同じような問題が出るので、過去問の分析は非常に重要なのです。
ですから、本問の出題当時は平成15年度問題2を解いていれば、少なくとも肢エとオは簡単に正誤の判断をつけられたはずですから、後は常識的に考えて解けばよかったわけです。
まずは、過去にも類似問題が出題された肢エとオから簡潔に解説していきましょう。
<肢エ>
調停などの裁判以外の紛争解決方法=ADRで、上記の平成18年度問題1でずばり聞かれていますね。
この肢エが布石となって、出題されたのでしょう。
示談(和解契約)等で当事者の意思に基づいて紛争解決をしますから、法の基準によらない場合もあります。
よって、肢エは、正しいです。
<肢オ>
上告審は法律審ですから、原則として、事実認定はしません(刑事訴訟法405条参照)。
しかし、重大な事実誤認があった場合は、法律違反に匹敵しますから、上告裁判所でも審理の対象となります(刑事訴訟法411条3号)。 よって、肢オは誤りです。
次に、平成19年度問題1の肢5とほぼ同じ問題である肢イを見ていきましょう。
<肢イ>
平成19年度問題1の肢5にもあるように、法令等の憲法違反の判断や最高裁判所の判例を変更する判断をするときは、大法廷で裁判しなければなりません。
これは、単純知識問題ですので、知っているかどうかだけの問題です。
ただ、この知識は別のところで役に立つことがあるのです。
おそらく気にもしなかったところだと思います。
以下のように、本試験の問題文の最後に「小」という字が書かれているときがあります。
平成19年度問題34
(最二小判平成16年11月12日民集58巻8号2078頁以下)
平成16年度問題4
(平成8年3月19日 最高裁判所第三小法廷判決)
これらの場合は、小法廷で判決されていますから、出題されている判例が、憲法違反や判例変更ではないことを示唆しています。
ですから、例えば、未知の判例に基づく出題がされて、最後に上記のように「小法廷」などがついていたら、その判例が憲法の判例ならば、違憲判決ではないことがわかりますし、最新の判例だとしたら、変更がないので、従来の判例の考え方に従えばよいということになります。
前者のように出題された判例が憲法判例の場合、例えば、「この判例の考え方と異なるものを選べ」というような問題だとしたら、判例を読まなくても、違憲になりそうな内容の肢を選べば、もうそれで答えが出てしまいますね。
また、後者のような場合、最新の判例を知らなくても、それに類似する過去の有名判例は必ずあるはずですから、それを思い出して、同じように理由と結論を考えて解けばよいのです。
このように、実は、この何でもないような知識が問題を解くヒントにもなるのです。
今度から問題文を注意深く確認してみてください。
もっとも、H19問題1の肢5と異なるのは、「大審院」が問題文に含まれているところです。
「大審院」とは現在の最高裁判所ができるまで、それに相当する裁判所でした。
しかし、「大審院」は、明治憲法下における裁判所、すなわち主権が天皇にある時代の裁判所です。
これに対して、最高裁判所は、第二次世界大戦後にできた日本国憲法の下で機能する裁判所です。
つまり、主権が国民にある現代の裁判所です。
わが国の場合は、単に憲法が改正されたというレベルのものではなく、国家の主権そのものが天皇から国民に変わった、ある意味革命的な憲法の制定だったのです。
ですから、最高裁判所と大審院では、その考え方の根本が異なります。
明治憲法では、いわゆる個人の尊厳にあたる人権思想などはなく、あくまでも天皇に与えられた臣民権にとどまり、違憲審査権などもありませんでした。
考え方の根本が同じである最高裁の従前の考え方を変更するために、大法廷で最高裁判所の裁判官全員の判断に委ねられるのです。
ですから、そもそも考え方の根本が異なる大審院の考え方を変更することは、従前の最高裁の考え方を変更することと同じとはいえません。
それゆえ、「大審院」のした裁判と異なるときには、大法廷で裁判をする必要がないのです。
よって、肢イは誤りとなります。
最後に、肢アとウを見ていきましょう。
<肢ア>
裁判拒否ができるとしたら、裁判を受ける権利(憲法32条)を害しますし、終局的に裁判所での紛争解決することができなくなりますから、裁判制度そのものの意義が失われます。 よって、肢アは、正しいです。
<肢ウ>
これは、常識問題ですね。
民事裁判の審理の対象が、給付請求権等の権利の存否等であるのに対し、刑事裁判の審理対象は被告人の刑事責任の有無ですから、両者の審理対象が異なります。
そうすると、民事裁判では、不法行為が成立し、損害賠償請求が認められたとしても、刑事裁判では、処罰に値する違法行為がなかったとして無罪になることもあるのです。
これは、民事裁判では、50%を超えて、裁判官に権利の存否の確信を与えれば、訴えが認められるのに対して、刑事裁判では、裁判官に合理的な疑いを超えて有罪であるとの確信を与えなければならないということからも、両裁判では異なる事実認定がなされる根拠になるでしょう。
例えば、有名どころでは、アメリカですが、O・J シンプソン事件などは、まさに民事裁判で負けて、刑事裁判で無罪を勝ち取ったという裁判でした。
日本の裁判制度は第二次大戦後に整えられましたから、民事訴訟法も刑事訴訟法も英米法の影響を強く受けているので、同じことがいえるのです。
よって、肢ウは正しいです。
以上より、誤っているのはイとオの2つですね。