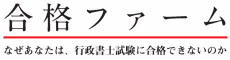民法 債権 (H24-34)
不法行為に基づく損害賠償に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア Aの運転する自動車がAの前方不注意によりBの運転する自動車と衝突して、Bの自動車の助手席に乗っていたBの妻Cを負傷させ損害を生じさせた。CがAに対して損害賠償請求をする場合には、原則としてBの過失も考慮される。
イ Aの運転する自動車と、Bの運転する自動車が、それぞれの運転ミスにより衝突し、歩行中のCを巻き込んで負傷させ損害を生じさせた。CがBに対して損害賠償債務の一部を免除しても、原則としてAの損害賠償債務に影響はない。
ウ A社の従業員Bが、A社所有の配達用トラックを運転中、運転操作を誤って歩行中のCをはねて負傷させ損害を生じさせた。A社がCに対して損害の全額を賠償した場合、A社は、Bに対し、事情のいかんにかかわらずCに賠償した全額を求償することができる。
エ Aの運転する自動車が、見通しが悪く遮断機のない踏切を通過中にB鉄道会社の運行する列車と接触し、Aが負傷して損害が生じた。この場合、線路は土地工作物にはあたらないから、AがB鉄道会社に対して土地工作物責任に基づく損害賠償を請求することはできない。
オ Aの運転する自動車がAの前方不注意によりBの運転する自動車に追突してBを負傷させ損害を生じさせた。BのAに対する損害賠償請求権は、Bの負傷の程度にかかわりなく、また、症状について現実に認識できなくても、事故により直ちに発生し、3年で消滅時効にかかる。
1 ア・イ
2 ア・エ
3 イ・オ
4 ウ・エ
5 ウ・オ
解答 1
ア 正
過失相殺(第722条2項)からの出題です。
722条2項
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
本問のポイントは、「原則としてBの過失も考慮される。」の部分です。
被害者側の過失の問題ですが、この部分は、問題文としてはあまり適切ではありません。そのため、迷った方もいたでしょう。ただ、組み合わせ問題であり、他の肢で誤っているものがありますので消去法で正解したいところです。
被害者にも過失があった場合は、これを斟酌して損害額を算定するのが公平なので、過失相殺が認められています。
もっとも、債務不履行に基づく損害賠償請求に対する過失相殺(418条)と異なり、必ず斟酌されるわけではありません。
例えば、本問のような交通事故の場合、歩行者がよそみをしていたことも事故の要因の一つであったとしても、これを考慮するかどうかは、裁判所の判断に任されているということです。
不法行為の場合は、被害者側に過失があっても、できる限り加害者に損害を負わせる方が公平だと考えられているのです。
ですから、後述する判例からもわかるとおり、「原則としてBの過失も考慮される。」というのは言い過ぎです。
原則として必ず被害者側の過失も考慮されるという読み方もできてしまいますね。
せめて、「Bに過失がある場合、原則としてBの過失も考慮することができる。」くらいの文章の方がより正確でしょう。
判例(最判昭51年3月25日)を紹介しておきます。
「傷害を被った妻が右第三者に対し損害賠償を請求する場合の損害額を算定するについては、右夫婦の婚姻関係が既に破綻にひんしているなど特段の事情のない限り、夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができるものと解するのを相当とする」
イ 正
共同不法行為からの出題です。
第719条1項
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
AB双方の過失によって、Cに損害を与えているので、共同不法行為が成立します。この場合、被害者Cに対して、AとBは連帯責任を負います。
ですから、被害者は、AとBに対して損害賠償額について全額請求することができるのです。
このような連帯債務を不真正連帯債務といいます。
当事者の合意に基づく連帯債務とは異なるで「不真正」とつきますが、負う責任は同じです。
ただし、被害者が共同不法行為者の一人に対して履行の請求をしても絶対効がなく、時効の中断は他の共同不法行為者との関係では生じないのです。また、被害者が共同不法行為者の一人に対して債務免除しても適用がありません。
元々別に責任を負うべき者なので、この点が通常の連帯債務と異なるのです。
もっとも、被害者が共同不法行為者の一人に対して債務免除する際に、他の共同不法行為者の残債務をも免除する意思を有している場合、他の共同不法行為者にも残債務の免除の効力が及ぶという判例(最判平成10年9月10日)がある点に注意しましょう。
ウ 誤
使用者責任(715条)における使用者から被用者への求償権の問題です。
第715条
1 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
本問のポイントは、「A社は、Bに対し、事情のいかんにかかわらずCに賠償した全額を求償することができる。」の部分です。
使用者は被用者の活動によって利益を得ているので、被用者が他人に損失を与えてしまった場合は、その損失を負担すべきであるという報償責任の原理を基礎とします。
そのため、使用者責任は、被用者の代位責任であるため、使用者が被用者に対して求償することができます。
もっとも、事情にかかわらず全額被用者に対して求償できるのであれば、上記の使用者責任が、報償責任であるという趣旨に合致しませんね。
ですから、損害の公平な分担から、当事者の事情を考慮して一定の限度で求償できるのです。
判例(最判昭51年7月8日)を紹介しておきます。
「使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである」
エ 誤
工作物責任(717条)からの出題です。
第717条
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
本問のポイントは、「線路は土地工作物にはあたらないから」の部分です。
工作物責任とは、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があり、その瑕疵によって他人に損害を生じさせた場合に、その工作物の占有者および所有者に特殊の責任を課したものです。
土地の工作物とは、土地に接着して人工的に作出した物およびそれと一体となって機能している物をいいます。
そうすると、線路も土地に接着して人工的に作出した物およびそれと一体となって機能している物なので、土地の工作物にあたるのです。
判例(最判昭46年4月23日)を紹介しておきます。
「列車運行のための専用軌道と道路との交差するところに設けられる踏切道は、本来列車運行の確保と道路交通の安全とを調整するために存するものであるから、必要な保安のための施設が設けられてはじめて踏切道の機能を果たすことができるものというべく、したがって、土地の工作物たる踏切道の軌道施設は、保安設備と併せ一体としてこれを考察すべきであり、もしあるべき保安設備を欠く場合には、土地の工作物たる軌道施設の設置に瑕疵があるものとして、民法717条所定の帰責原因となるものといわなければならない」旨判示している。
オ 誤
不法行為による損害賠償請求権の期間の制限(724条)からの出題です。
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
本問のポイントは、「症状について現実に認識できなくても、事故により直ちに発生し、3年で消滅時効にかかる。」の部分です。
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間で時効消滅します。
立証の困難性や法律関係の早期確定のためです。
この場合の損害を知るとは、損害発生の事実を知ることであって、損害の程度また数値を知る必要はありません。
そうすると本問は正しいとも思われます。
しかし、事故から3年経過後に、後遺症が発生したような場合にもこの原則を貫くと不都合が生じます。
事故当時には予想できなかった損害であっても、その後に治療が必要となった場合に、その治療費を損害賠償として加害者に請求できないと不公平ですね。
そこで、このような後遺症損害による治療費については、その治療を受けるまで時効は進行しないのです。
判例(最判昭42年7月18日)を紹介しておきます。
『不法行為によって受傷した被害者が、その受傷について、相当期間経過後に、受傷当時には医学的に通常予想しえなかった治療が必要となり、その治療のため費用を支出することを余儀なくされるにいたった場合、後日その治療を受けるまでは、治療に要した費用について民法第724条の消滅時効は進行しない。』