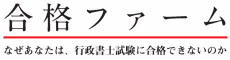民法 物権 (H25-29)
Aが自己所有の事務機器甲(以下、「甲」という。)をBに売却する旨の売買契約(以下、「本件売買契約」という。)が締結されたが、BはAに対して売買代金を支払わないうちに甲をCに転売してしまった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
1 Aが甲をすでにBに引き渡しており、さらにBがこれをCに引き渡した場合であっても、Aは、Bから売買代金の支払いを受けていないときは、甲につき先取特権を行使することができる。
2 Aが甲をまだBに引き渡していない場合において、CがAに対して所有権に基づいてその引渡しを求めたとき、Aは、Bから売買代金の支払いを受けていないときは、同時履行の抗弁権を行使してこれを拒むことができる。
3 本件売買契約において所有権留保特約が存在し、AがBから売買代金の支払いを受けていない場合であったとしても、それらのことは、Cが甲の所有権を承継取得することを何ら妨げるものではない。
4 Aが甲をまだBに引き渡していない場合において、CがAに対して所有権に基づいてその引渡しを求めたとき、Aは、Bから売買代金の支払いを受けていないときは、留置権を行使してこれを拒むことができる。
5 Aが甲をまだBに引き渡していない場合において、Bが売買代金を支払わないことを理由にAが本件売買契約を解除(債務不履行解除)したとしても、Aは、Cからの所有権に基づく甲の引渡請求を拒むことはできない。
解答 4
本問は、担保権や抗弁権に関する総合問題であって、一見すると先取り特権や所有権留保などあまり見慣れない問題がでているので難しく感じるかもしれません。
しかし、実際は、同時履行の抗弁権と留置権との違いがわかっていれば容易に正解することができます。もっと端的にいうと、誰にでも主張できる物権と当事者にのみ主張できる債権との違いがわかれば正解できる問題なのです。
このように一見マイナーな分野からの出題であっても聞いている内容は簡単な問題も出題されるのであまり難しく考えずに日ごろから素直に問題に向かって解く姿勢を身に付けるようにしましょう。
肢1 誤
333条に関する問題です。
第333条
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
動産については、動産譲渡登記を除いて、公示の方法がないですから、動産を譲り受ける第三者は、その動産に先取特権の効力が及んでいることを確認できないのが通常です。
そのため、そのような第三者を保護して動産取引の安全を図るために、先取特権の効力が及んでいる動産を譲り受けても、その動産に対して先取特権を実行することはできないと規定したのです。
この場合、第三者の善意・悪意は問いません。第三者への引渡しで先取特権が及ばないと画一的に処理することにしたのでしょう。
したがって、本問においてBが動産甲をすでにCに引き渡した以上もはやAはCに対して先取特権を実行することはできないのです。
肢2 誤
売買契約のような双務契約である場合、目的物の引渡しと代金の支払いは公平の観点から同時に履行しなければなりません。これを法的にいうと、代金支払債務には同時履行の抗弁権が付着しているといいます。
同時履行の抗弁権とは、例えば、契約当事者の一方がいまだ履行していない段階で、一方が他方に履行を請求しても、他方が「あなたも履行しないと私も履行しませんよ」という抗弁を一方に主張できるものです。
もっとも、同時履行の抗弁権は契約上の効力に過ぎないので契約当事者にしか主張できない点が留置権と異なります。したがって、同時履行の抗弁権は第三者に対しては主張できないため、CがAに対して所有権に基づいてその引渡しを求めたとき、Aは、同時履行の抗弁権を行使してこれを拒むことはできないのです。
肢3 誤
所有権留保も譲渡担保と同様に非典型担保の一種です。
例えば、自動車のローンについては、所有権留保という制度になります。
自動車売買の支払いが完了するまでは、売主であるディーラーまたはローン会社の所有物として所有権が留保され、支払いの完了によって購入者に所有権が移転することになります。
譲渡担保と機能は似ていますが、譲渡担保は、契約によって売主にあった動産の所有権が買主に移転するのに対して、所有権留保は契約によって支払いが完了するまでは動産の所有権は売主(ディーラーまたはローン会社)に残る点で異なります。
したがって、AB間に所有権留保特約が存在すれば、甲の所有権はAの残るため、Cは承継取得することはできないのです。
肢4 正
留置権というのは、他人の物を留置することによって、相手方に心理的圧迫を与えて弁済を間接的に強制する担保物権です。
つまり、「お金を払わないと物を渡さないぞ」ということです。
担保物権であるので契約の当事者のみならず第三者に対しても主張できる点が当事者に対する抗弁権である同時履行の抗弁権と決定的に異なる点です。
したがって、本問のように、動産甲がA→B→Cと譲渡され、まだBがAに売却代金を支払っていない場合、Aは代金が支払われるまで甲を保管し続けることができるのです。
肢5 誤
解除前の第三者(545条1項)については、法律関係を明確にするため、対抗力の有無によって、画一的に処理することにしたのです。
動産の場合は、引渡し(178条)が対抗となります。
したがって、Aが甲をまだBに引き渡していない場合であれば、Aに動産の占有があり対抗力があるので、Cからの所有権に基づく甲の引渡請求を拒むことができるのです。